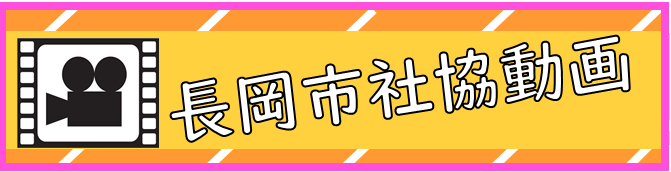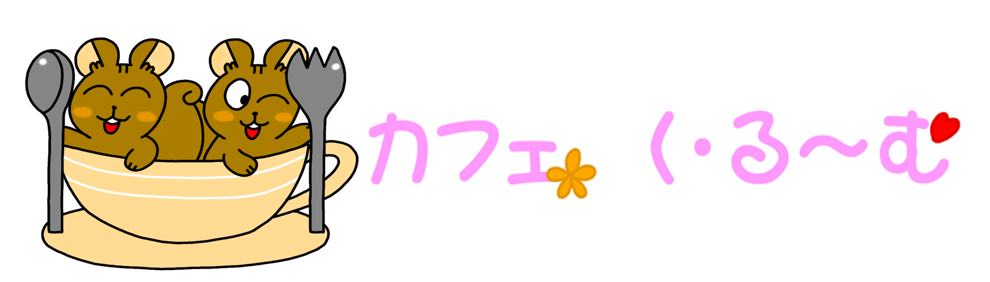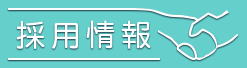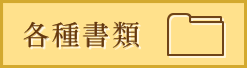ふれあいのまちづくり事業と長岡市福祉コミュニティ構想
私たちの国は、社会・経済状況の変化による一層の少子高齢化や核家族世帯の拡大、それに伴う地域関係の希薄化等、今後の社会福祉のあり方が大きな課題となっています。多様な福祉需要が出てくる中で、年齢や障害の有無にかかわらず、誰もが安心して暮らせる地域づくりがますます必要となってきます。
長岡市社会福祉協議会は、市内41地区の地区社会福祉協議会・地区福祉会と協働で、市民が主体となった以下の互助活動を推進しています。
- 地域ささえあい事業
- ふれあい型食事サービス事業
- 小地域ネットワーク活動
- ふれあい・いきいきサロン事業
これまで、市民主体の福祉活動が飛躍的に発展した理由として、平成6年に地域支援体制の整備を目的とした国庫補助事業である「ふれあいのまちづくり事業」の実施と同年に策定された「長岡市福祉コミュニティ構想」があげられます。
「長岡市福祉コミュニティ構想」では市民の福祉コミュニティ意識の醸成に向け、構想実現への具体的方策として、「地域福祉エリアの設定」「地域の拠点となる場所の確保」「地域の核となる人材の確保」「地域における推進体制の整備」の4点が盛り込まれました。
そこで、従来の地区社会福祉協議会・地区福祉会の組織・基盤の強化とともに、「福祉コミュニティ推進コーディネーター(地区コーディネーター)」が各地区に配置されました。
地区コーディネーターは地区内の互助活動のコーディネートや地区社会福祉協議会・地区福祉会の運営に中心的な立場で加わることにより、各地区の特性に合った活動推進の原動力となり、地域福祉活動の推進役・調整役として重要な役割を果たしてきました。
平成16年、旧長岡市における地域施設のコミュニティセンター移行に伴い、各地区において福祉コミュニティづくりの推進を図るため、コミュニティセンターごとに福祉担当主事が配置されました。
なお、合併地域においても、現在9つのコミュニティセンターを設置し、コミュニティ活動を総合的に推進、支援しています。